| □ |
AX−6までの大半のゲームはUTMC関係者が作成したものです。
|
| □ |
UTMC以外の著者は、浅野君 (いまは名前が変わって、
河東(かわひがし)教授という数学者になられました)
[*1]
が作った「マイクロオセロ」と、
あと桜田君(出版部のアルバイトだったと思う)
[*2] が作った
「シャット・ザ・ボックス」くらいだと思います。
|
| □ |
UTMCはインベーダーで一世を風靡したT社と、ある内容の契約を結んでいました。
契約を結んだのは、私の一年上の部長の鈴木さん。
雑誌「週刊朝日」でも紹介された「万引少年/少女」や、工学社(I/O)
から出版されたフライトシミュレータ「ザ・コックピット」を作った方です
[*3]。
鈴木さんは、私と一緒に朝日新聞社に入り、数年後に一緒に朝日ネットを立ち上げて、
現在に至っています。 私は大学入学直後にアップルII(36万円)を購入して、
少ない小遣いからヒーヒー言いながら月賦の支払いをしていましたが、
T社からもらったお金で完済することができたものです。
|
| □ |
T社が提供する条件も決して悪くはなかったのですが、製品化に直接結びつかない仕事は、
ゲーム制作動機的にはチと弱いところがありました。
そこに、アスキーの話が持ち上がりました。 UTMCの部員で、
後にAX−1のほとんどを作った安田君[*4]
がアスキーでバイトをしており、第二出版部部長の松田充弘さんが立てたPC−6001用の
シリーズものの企画に参加しないか、という話を持ってきたのです。
|
| □ |
松田さんは、アップルのゲームと国産ゲームのあまりの差に憤りを感じており、
アップルにできることが国産機にできないはずはない、という信念のもと、
良質のゲームをブック型パッケージングで安価に提供したい、
という強い意思を持っていました。 われわれも、カセットテープにコピーで作った説明書
を入れたようなゲームには辟易していましたから、
一も二もなくやろう、と思ったメンバーが多かったと思います。
UTMCからは、三橋君[*5]、
広瀬君[*6]、
藤沢君[*7]、
阿久津君[*8](みな2年生になったばかりのころ)
などが参加しました。
ただし、クラブとしてアスキーとの契約を結んだわけではなく、あくまで個人としての参加でした。
|
| □ |
AXのゲームの各タイトルは、メンバーが「こういうのを作りたい」と言ったものが、
ほぼそのまま受け入れられていたと思います。
中には、それまでにクラブで作ったもののアレンジもありました。
たとえば、「宇宙輸送船ノストロモ」は、私がクラブに入って最初に書いたゲーム
(PET−2001で開発)でした。
それを三橋君がAXシリーズ用に改良したものです。
|
| □ |
オリオンとは関係ありませんが、「クエスト」は、
杉山さんという人が月刊アスキーに掲載した3Dリアルタイム迷路が元になっています。
|
 |
[*1] |
河東(旧姓・浅野)泰之氏。 UTMCには所属していなかったが、この方も東大出身。
AX−3 に収録されている全作品(「マイクロセロ」「インターファイト」
「コズミックレボ」「スロットポーカー」)、及びAZ-1「フライトシミュレーター」の作者。
河東氏のプロフィールページ
によると、UTMCに入ったものの、すぐに退部したとのこと。
|
 |
[*2] |
桜田幸嗣 氏。 AX−4:「シャット・ザ・ボックス」の作者。
|
 |
[*3] |
鈴木浩氏。 「万引少年」は店員の視線を逃れて、お店の商品を盗るゲーム。
「マイコンBASICマガジン」82年7月号にはPC-6001への移植版も掲載された。
ただし、鈴木氏はこの移植版には関与していない。
|
 |
[*4] |
安田吾郎氏 。
AX−1:「アラビアン・ラプソディ」「ブロックくずし」「ハイスピード・バリケード」、
AX−6:「マスターマインド」の作者。
|
 |
[*5] |
三橋正邦氏。「大葉浩美」は三橋氏のペンネーム。
代表作はAX1〜4 及びAX6のデモンストレーション、AX−2:「ノストロモ」、AX−5:「クエスト」など。
|
 |
[*6] |
ペンネームは「両津順平」氏。
AX−2:「スティールエイリアン」、AX−4:「カーレース」、AX−6:「パワードナイト」の作者。
|
 |
[*7] |
藤澤健氏。
AX−1:「サイモン」、AX−2:「イン・ザ・ウッズ」、AX−6:「ヘッド・オン」の作者。
|
 |
[*8] |
ペンネームは「杉本薫」氏。
AX−2:「デュアル・エイリアン」、AX−4:「ブラックホール」の作者。
|
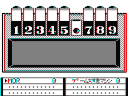 「シャット・ザ・ボックス」は、 AXシリーズで、初めてモード4を使用したゲーム。
モード4は本来は白黒2色だが、色ずれで赤や青が出力された(右写真)。
「オリオン」ではこの色ずれを利用してモード4で白黒赤青の4色表示を実現した。
ただし、本体やモニターの精度によっては色ずれが発生しない場合もあった。
「シャット・ザ・ボックス」は、 AXシリーズで、初めてモード4を使用したゲーム。
モード4は本来は白黒2色だが、色ずれで赤や青が出力された(右写真)。
「オリオン」ではこの色ずれを利用してモード4で白黒赤青の4色表示を実現した。
ただし、本体やモニターの精度によっては色ずれが発生しない場合もあった。