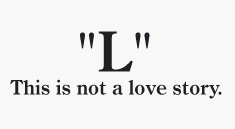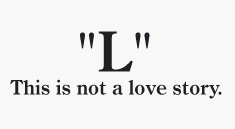|
28になった僕が14の頃の恋話をするのもちょっと変かもしれない。でも、今目の前
にある彼女遺影を見ていると、あの頃を思い出してしまう。ま、仕方の無い事だろう。
作家になって3年、自分の事をネタにするほどネタに飢えてはいないが、この自白を読
んでくれている方々には、この自白を許して貰いたい。
でも、28に何か自分に残せるものを書きたいと思っていたのでそれはそれでいい事な
のかもしれない。何故28か?読者の方々は不思議に思うだろう。それは28がピュアな
数字だからだ。28、1×28、2×14、4×7かけ算で見た場合この数字で構成され
る28。しかも1+2+4+7+14=28。たしてもかけても28になるこの数字の構
成に、僕はなんらかの純粋さを覚えた。だから自分が28の時に何か自分の為の物を書こ
うと思った。そして、僕は彼女の遺影の前で決めた。彼女との事を書こうと。
僕が彼女に会ったのは14の頃、中学のクラス替えで一緒になったという所に始まる。
今思うと中学の頃っていうのは今の自分に比べるとはるかに子供だった。あの頃の自信に
も似た、大人のフリみたいな物には苦笑するが、何事も、年を経てみないとわからない。
ま、でも僕に取っては、去年の事も子供のような印象にしか残らないが。
その彼女といつ友達の関係になったかは今を持って不明である。共通の友達がいたわけ
でもないし、席がすぐ隣だったわけでもない。コレといった、ドラマチックな出会いとい
う物がないので、読者の方々には、「なんなんだコレは」と思われるかも知れないが、前
述の通り、彼女はもうこの世にはいないわけである。僕も多少の動揺を隠せないようなの
だ、今後気持ちに任せて文章に怪しい言語や間違った文法が飛び出すかもしれないが、そ
れは、僕自身のこころの揺れなので、気にしないで読み進めて欲しい。もし、酷いような
ら、この感情に任せた作文は、自ら封印するので、読者の目には触れる事がないかもしれ
ない。
でも、彼女とはどうゆうきっかけで、話すようになったんだろう。あの頃の僕は、一応
文学青年で通っていて、ヘルマン・ヘッセやカミュをしつこく読んでいた。部活動は文芸
部で、彼女はバレー部だった。全くを持って接点がないだが、これ以上続けても面白くな
いので、彼女との出会いは省く。でも、それが人生だろう。きっかけは、とても些細で、
映画のような運命的な物なんて物は殆どあるわけがない。
彼女とよく話すようになったのは二学期以降。
クラス内の班編成で、彼女が班長の所に僕が入ったのだ。
この編成は、まず班長を立候補で選出し、班長会議のときにクラスの中から班長が班員
を取り合うという形で、この取り合いが結構壮絶なので、僕は一学期で班長を辞めてしま
った。彼女は一学期に続き二度目だった。
「だって、仲良しかつ重要な戦力だもん」
僕を選んだ理由を聞いたらそう答えた。この時の僕と彼女は”仲良し”というには、ま
だ会話が足りないように思えた。
この時の「重要な戦力」の意味は後々理解できた、二学期には文化祭があるのだ。
僕の当時の文才みたいな物は中学生の中ではかなりの方だったらしく。班外からの発表
文の構成を頼まれたりもしたが、班長である彼女はマネージャーさながらに、自分の班以
外の注文はつっぱねた。僕としては一年の時からの恒例と思ったので、幾つか彼女に隠れ
て構成をしたが、彼女は読解能力が高いらしく、いくらごまかしても僕の書いた物を見つ
けると抗議を言いにいった。このことに関しては、文学部の文化祭用の文集の事で、彼女
が僕には書かせないでくれと示談しに行った位だった。おかげで自分の班以外の仕事は殆
ど無く、作家を夢見る中学生は、ここで最初の売れっ子作家の苦しみを味わう。
が、この有能な作家はマネージャーによって多量な仕事をされてるか言えば、そんな事
は全然無く、彼女の話し相手としての立場に立っていた。勿論僕の手を借りたい他の班の
連中からは良くは思われないのは当然だが、彼女はおしゃべりには長けていたので、どん
なに語調の強い娘が来ても、ものの五分で彼女が勝ってしまった。酷いときは相手が泣い
てしまう時さえあった。
ま、でも泣いてしまうと流石に悪いと思うらしく、期間限定で僕は献上させられた。そ
の時仕事量はハンパな物ではないが、恒例行事モードのままくすぶっていた感のある僕と
してはスタートダッシュする分には、大したものではなかった。
こうすると泣けば僕が借りられると言う事で泣き虫一同彼女の所に参戦したが、同じ手
は二度も通じず、僕はまた売れっ子失業状態になった。
彼女と話す話というのは、多岐に渡っていてそれはそれで楽しかった。今までの人生の
中で、最も中身の濃い会話をした女の子は彼女以外いない。その大半は彼女の興味のある
事で、僕の知らなかった事も多く、良い刺激になった。彼女が話しているときにちょこち
ょこっとするかわいい仕草を気になり出したのもこの頃からになる。
「ねぇ、脚本って書かないの?」
唐突に聞いてきた、文化祭前日の帰り道で、放課後というには遅すぎる時間帯、秋まっ
ただ中だが、少し空気が冷たかった。僕はバス通学だったので、駅の方に向かうのだが、
彼女はその駅の向こう側なので、駅までは一緒だった。
「脚本て何の?」
「ドラマとか映画とか」
その当時、と言っても今でもそうだが、小説以外文章の類を書きたいと思った事はなか
ったので、難しい質問をしてきたなと思った。
「んーわかんない」
と答えるだけがその時の最大限の返事だった。彼女は少しだけ何か思い詰めたような表
情をし、話題を別な物に変えた。
(ここで、彼女の葬儀の際彼女の親御さんから、一冊のノートを渡された事を記してお
く。そのノートの内容は、僕の処女作「からたち」を舞台化案が書かれていて、台本にも
なっていた。)
文化祭当日、僕らのクラスの行った展示は、概ね好評だった。扱った題材その物は些細
な物だったが、こうゆう時のクラスの団結の良さというのは、安い青春物その物の雰囲気
だが、それはそれで気持ちのいい物に違いなかった。みんなこの雰囲気に酔っていた。こ
のメンバーでやって行けるのも、あと一年程しかない。三年になったら、嬉しくもあり寂
しくもある盛り上がりかたをするんだろう。
僕と彼女は、この日を境により一層仲良くなっていった。恋人同志とかそうゆうんじゃ
なく、友情にも似た良い仲だった。彼女とは三年の時も同じクラスだった。
三年になってから、彼女の恋愛相談を受けるようになっていた。普通同性に持ち込んで
くものだろうと思いつつも、その相談にはのってあげた。でも、その頃には僕は彼女の事
をかなり気になっていたので、相談を持ち込んでくると、勿論応援するように、でも正直
に相談にのった。少し意地悪い答かたもした。やきもちだ。
それから相談を持ちかけてくると自分がブルーになっている感じがした。彼女が聞いて
くるばっかりなので、それに何らかの不安を感じてきていたのかもしれない。でも、彼女
が好きになっている男には絶対しないような質問も聞いていたので、その点については、
何らかの優越感に浸っているという、げんきんさがあった。
そのほったはれた話でいきなり泣き出す事もあった。こうゆう時は困った。とにかく何
らかの方法で彼女を慰めるなり励ますなりしないといけないのだが、こういった場面での
言葉がなかなか見つからなかった。小説書いてて変だなと思う方もいるだろうが、得てし
てそんなものだ。大抵は、自分を有利にする為のずるい言葉しか想い浮かばなかった。そ
の言葉を使うのを僕の良心が妨げた。かと言って、抱きしめてあげるのも露骨すぎるので
彼女の泣き声に混じって、判断に悩む僕の顔と、肩にかけようとしているが緊張で動かな
くなって震えている手とがあり、周りから見れば僕が泣かしたかのような構図になってい
たに違いない。そのような中で唯一言えたのが、
「ガンバレ」だった。
何をどうガンバレなのか自分でも良く解らなかったが、その時はその言葉しか使っては
いけないような気がしていた。彼女も「うん、頑張る」と言っていた。彼女からしてみれ
ば、次の恋をがんばるという意味だったかもしれない。
かくして、彼女にとって文化祭の有能な戦力だった僕は、いい話し相手から、恋の相談
役へと僕の想いとは裏腹に格上げしていったわけだが、このまま高校も同じかといえば、
そうは行かなかった。彼女は女子校に行ってしまったのである。さすがに女子校を受験す
るわけにはいかない。
「くればいいのに」
それが彼女の意見だった。なら、そっちがこっちに来て欲しいものだが、受験の頃に大
きく失恋して、電話してきて電話口で泣いているだけに、その頃はせめて学校の中で位は
男は見たくなかったのだろう。その点で考えれば賢明な選択かも知れない。
高校が違うために、通学時間のほんの15分位しか会わなくなったが、その分電話が増
えた。彼女の話は、恋愛相談から、学校の話へと変わっていた。男子校よりすさまじいか
もとか、冬はスカートのしたにジャージをはいて過ごすとか、とにかく色々な女子校ノウ
ハウを教えてくれた。その中で男が使えそうなネタなどは無いに等しいが。
結局、彼女が女子校に進学した事が、僕に取って何らかの変化を起こさせた。
その変化とは焦りだ。
つまり、彼女が女子校に通う事によって、共学の女子よりも同年代の男子に会う時間と
云うのは、今までに比べ減るのは当然の事で、その面に関しては何の焦りも無かったが、
よくよく考えれば、僕もその中の一人である事には変わらない。その上、彼女に会う時間
は極端に減ったのだ。僕はその時間に何をしているのかが気になった。
気になって気になって気になった結果が、告白だった。
”その日”は意外と早く来た。ただ単に焦っていただけと言えば、実も蓋もないのが。
割と静かな、風の気持ち良い午後だった。呼びだしたのか、呼ばれたのかはわからない。
毎日通学時には会っているのに、お互い「久しぶり」が挨拶だった。
最初は彼女の例の相談めいた雑談に始まって、いつものように話をした。ただ僕には告
白という視野狭作にもってこいのイベントがあったため殆どてきとうな相づちで交わして
いた。さすがの彼女も疑問に思ってか、「どうしたの?」と聞いてくる。多分気分の悪そ
うな顔でもしていたんだろう。こうった場合往々にして伏線という物は存在しない。僕も
その例にもれず、告白した。
この告白、今となってはどうゆう意味を持つ物か、わからない。この時の自分は”せめ
て自分が好きだって事を彼女に知っていて貰おう”というやる気があるのか無いのかハッ
キリしない理由が頭の中を駆け巡っていた。フラレた時の為のダメージを少なくするため
の最低な方法の一つだが、僕はこの時のこの理由になんらかの純粋さを見いだしていたの
も事実だ。
彼女は、
「ダメだよ」
の一言。そして理由を聞く前に
「だって、私。一人のひとで終わりたくないもん。経験っていうのも変だけど、いろん
な男の人とセックスしてみたいし。」
それが彼女が僕をふる理由だった。
彼女の言葉をどう解釈すればいいのか、解らないが、プラス方向で解釈しても、マイナ
ス方向で解釈しても、自分の気持ちが複雑になるのは確実で、この時の彼女の気持ちとい
うのは読者の方々にお任せする。
ただ、少なくとも、彼女のあの一言は、僕にしか言わないというのは、解っていた。普
段ああゆう事をいえるような性格ではないのだ。僕はある意味彼女を知りすぎていたのか
もしれない。
その日は泣いた。先ほどいった自分にダメージを与えない理由を与え込むより、お風呂
で静かに泣いた方が、気持ちは楽になった。
それを境に彼女には会わなくなった。
一週間後、彼女に彼氏ができたと風の噂で聞いた。彼女にとって”一人目”の男である。
そして、再び会ったのがこの霊前だ。病死だった。血液のどうのこうのと、彼女の母親
が僕に説明してくれたが、僕は彼女の亡骸の軽いウェーブのかかった髪を見つめていた。
多分病床で三つ編みをしていたんだろう。彼女はシャンプー以外の整髪料は嫌いだった。
彼女の母は、一通りの説明を終え、彼女を見つめている僕に気付き、彼女が「からたち」
の文庫本を大事そうに抱えて死んでいたと付け加えた。僕が彼女に小説を送ったのは「か
らたち」のみだった。他のは自分で買って読んでくれていたらしい。
僕は、彼女の書いた舞台版の「からたち」を読んだ。
あの長編がうまくまとまっていて、僕の書いた物よりもいいくらいだった。でも、舞台
化はしない。それが、彼女の遺言だった。
舞台化第二案と記された部分は告白のような日記になっていて、これを僕が読んでいる
事が前提になっていた。勿論あの時の告白の事についても書いてった。
けど、ここではお教えしない。彼女の遺言でという事はないのだが、今の所、自分だけ
の物にしておきたいのだ。ネタが詰まったら、書くとしよう。読者の方も、そういった意
味で、僕の書く小説のあらさがしをしてみるのも面白いかもしれない。
|